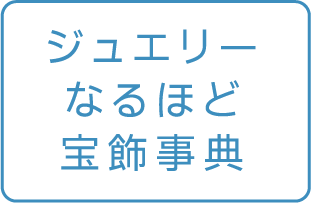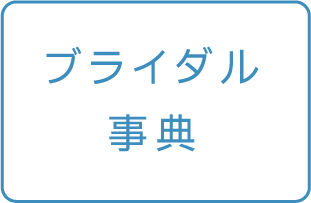エメラルドの宝石言葉 夫婦愛・清廉・幸福

コロンビア産のエメラルド
エメラルドは、ギリシャ語のスマラグドスから名付けられました。
厄災から身を守るといわれ、歴史的にもたいへん古く最も価値のある宝石の一つです。
心を穏やかにする美しいグリーンが神秘的です。
歴史
1818年に所在が確認された伝説のクレオパトラ鉱山(エジプト)では、古来淡い半透明の品質のエメラルドを産出していたといわれています。
メキシコからペルーにかけて広まっていた美しく大粒のエメラルドは、コロンビアを征服したメキシコ人によって本国に運ばれました。
カット
メキシコに運ばれたエメラルドは、カボションカット、ビーズカット、彫刻などに細工されて、ヨーロッパ、トルコ、イラン、インドの王室に持ち込まれました。
コロンビア産の特徴
コロンビア産エメラルドは、世界の産出量のおよそ50%を占めています。
約100の鉱山の中で代表的な鉱山はムゾー、チボー、コスクエス鉱山の三つです。
チボー鉱山・・・ブルーの強いグリーンエメラルドが産出されます。内包物が少なく透明度の高いものが多いのですが、品質は千差万別です。
ムゾー鉱山・・・濃いグリーンで柔らかな味を持っているのが特徴で、最高のエメラルドを産出するといわれているのがその割合は千個に一個程です。
コスクエス鉱山・・・淡めのグリーンで上記の鉱山と容易に判別できます。
◆ コロンビア・エメラルド物語 ◆
喜連川宝石研究所 所長 喜連川純氏著
びっくりの連続、ボゴタでのセミナー
さわやかな初夏の風にのって、新緑とエメラルドの季節がやってまいりました。
5月の守護石エメラルドの最大の産出国といえば、なんといっても南米コロンビアでしょう。
1972年、このコロンビアのある商社から、「偽物が出回って困っているので、エメラルドに関して講義をしてほしい」と依頼がありました。
海外でのゼミは初めてでしたが、早速必要な機材や鑑別器具を準備し、コロンビアにおもむいたのがその年の八月のことです。
首都のボゴタは、標高2600メートルの高地にあります。
講義期間は半月ということで、日本食は絶対必要と、紀文のイカの塩辛まで持って行ったのですが、宿舎で荷をほどいて見たら、なんと、塩辛の袋が気圧の関係でいまにも張り裂けんばかりに、パンパンに膨れ上がっているではありませんか。
そのうえ、さらに驚いたのは、ボゴタは一日のうちに一年分の四季があるということでした。
なにしろ、ほぼ赤道上に位置する高地ですから、気温の差が激しく、朝、昼、夕、深夜と春夏秋冬状態になるのです。
私はゼミのあいだ中、塩辛の袋みたいにおなかが張って、尾籠なはなしですが、オナラに苦しみ、服もいそがしく着たり脱いだりで、大変な思いをしながら講義をすすめることになりました。
つぎにショックだったのが、予備知識以上に泥棒、強盗、殺人事件の多い事です。
たとえば、空港からホテルまで乗ったタクシーは、見たこともない型のベンツでしたので、運転手に聞いてみると、ベンツのマークだけ泥棒市場で買ってきて着けたものということでしたし、ゼミの最中でもそのビルの下の道路でよくアメリカの観光客がひったくりにあり、騒いでいる光景を目にしたほどです。
◆ 危険がいっぱいのエメラルド鉱山へ ◆
そんなある日、せっかくここまで来たのだからぜひ鉱山を見ておきたいという思いがつのり、鉱山省におもむき、エメラルド関係の実権を握っているウゴ・カニサデス氏に会い、許可を出してくれるよう交渉しました。
ところが、彼いわく「それは大変危険なことである。ムソーの鉱山まで105km(東京-熱海ぐらい)あるし、途中、山賊がでることもしょっちゅうである。
だいいち戦後25年の間にエメラルド関係のトラブルだけで27万人もの人が殺されている。
あなたは27万一人目になってもいいのか」と、なかなか首を縦にふってきれません。
殺されるのは願い下げだが、そこをなんとかとねばり、やっと許可証をもらうことができました。
いまでこそ、ボゴタ、ムソー間は7時間のバスで結ばれておりますが、それとてムソーの町までで、鉱山はさらにそこから12キロも入らなくてはなりません。
私は、現地在住の日本人で今回のゼミの生徒であるS氏に運転を、K氏に通訳をお願いし、途中事故のないよう信頼度の高いトヨタのジープを練達して、3人ともまだ見ぬ鉱山をめざし、朝4時、寒くて真っ暗なボゴタの街を出発しました。
ムソーはアンデス山脈を太平洋側に下った標高600メートルぐらいのところにあります。
道路は石ころだらけのガタビシ道で、片側は断崖絶壁。
そのうえ道路標識は、兵隊の退屈しのぎの格好の標的として弾の孔だらけ、とても読めたものではありません。
さらに、途中、5回も、武器または盗掘したエメラルドを持っていないかと、検問所で兵隊に所持品から車の中まで徹底的に調べられ、やっとの想い出昼の11時半に目的地に着くことができました。
ここで鉱山の所長から「ようこそ遠いところを」と、ゴムのわらじみたいなステーキを御馳走になり、所長の案内で全員馬に乗って起伏だらけのだだっ広い鉱山を見て回りました。
◆ エメラルドのできかたと性質 ◆
ムソーの鉱山は、黒色の石灰質の頁岩(けつがん)でできているため、見渡す限り真っ黒な山です。
エメラルドはベリリウムとアルミニウムと珪酸が主成分であり、これにわずかなクロムが入って、あの美しいグリーン色になります。
古生代の頃、この頁岩層の近くに火成岩が入り込み、その火成岩がもってきた、エメラルドの成分の一部を含んだ熱水溶液が、頁岩の亀裂の中を通っているうちに、さらにほかの成分を溶かして化合し、石灰岩や頁岩の中で沈殿析出されてできたものです。
その温度も推定100~370℃と以外に低温低圧ですし、冷蔵庫の氷皿にゴミがあると氷の中にそのゴミが入ってしまうように、エメラルドができる前からあった鉱山も、当然、内部に取り込んで結晶ができてしまうわけです。
エメラルドに内包物が多く見られるのも、そのためということがお分かりいただけると思います。
また、着色物質であるクロムが結晶時に入り込むと、その結晶の成長に乱れを生じ、順調よく育った結晶というわけにはいきません。
よく「キズのないエメラルドを探すのは、欠点のない人間を探すようなものだ」という例えがあるのもそのためです。
おなじ主成分でできている、つまり、おなじべリル鉱物のアクアマリン(ブルー)、モルガナイト(ピンク)、ヘリドール(黄)は、エメラルドとできかたがまったく違うので、クリーンな状態の結晶で産出されます。
また、エメラルドは産地によってできるプロセスや成分比が違い、産地特有の内包物や緑色にも微妙な違いが見られます。
さて、夜道は危険だし、足元の明るいうちに帰ろうと、3時ちかくに鉱山を出て、ボゴタに無事着いたのが夜の11時頃でした。
◆ こうしてエメラルドは丈夫になった ◆
このようなエメラルドの欠点を補おうと、古代エジプト時代からいろいろな油を入れる試みがなされてきました。
それは油を浸透させると屈折率の関係で、キズが見事に消えてしまうのです。
もっとも、古代エジプトでは、神々に使える者や、捧げる供物には、みな、聖なる油オリーブ油を塗って清めていましたし、あのキリストという名前でさえ、ギリシャ語で「油注がれし者」という意味ですから、第一級の供物であるエメラルドには、当然、聖油が塗り込まれていたわけです。
物に油を塗ると透明感がでますが、神官たちは、それを“神が悪魔を追い払ったため”と考えたのでしょう。
エジプトのエメラルドは紀元前1650年頃から、紅海に面したスカイト山付近で採掘されていました。
はなしを戻しますが、私が行った頃のコロンビアではセダー油といって、ビャクシン科の木から取れる樹脂油を使用していました。
しかし、油はやがて抜けるし、抜けないまでも、ニスみたいに乾いてボケてもきます。
だいいち接着効果はまるでありません。
それでもキリスト教徒である彼たちは、なんの疑問ももたずに油を入れる作業をしていました。
宝石の美しさが永遠でなくてはなりません。
私は帰国してすぐ、この不安定さを解決しようと、難問題に取り組みはじめました。
試行錯誤のそんなある日、ふと奈良薬師寺の月光菩薩の首の修理法を思いだしたのです。
天平時代に作られたこの国宝の首は、昭和27年の吉野自身でぐらぐらになってしまいましたが、なにしろ首の目方が263キロもあるので、中に鉄筋を入れ、首をエポキシ樹脂で接着し、修理を完成させたということです。
これにヒントを得て、私はセダー油のかわりにエポキシ樹脂を浸透して固まらせ、エメラルドの美しさを永遠のものにしようと考えました。
コロンビアから帰国して10年目、1983年8月にやっとエポキシ樹脂によるエメラルドの強化保護処理を世界に先駆けて宝石業界に発表することができ、処理作業を開始する運びとなりました。
その後、1990年にアメリカでも独自の研究発表があり、それに前後して、本場コロンビアでもエポキシを使うようになり、いまや、エポキシ樹脂によるエメラルドの強化保護処理は、技術やエポキシの品質の差こそあれ、全世界的なものになって、「エメラルドは丈夫な宝石」に変身してしまったのです。
ただ、超音波洗浄機にかけると新しいキズができますので、これは避けるべきでしょう。
あ、それから、グリーンの色もくもりの日とか、夕暮れ後は濃く見えるものです。
エメラルドを買われるときは、できるだけ昼の光で選ばれた方がよろしいでしょう。